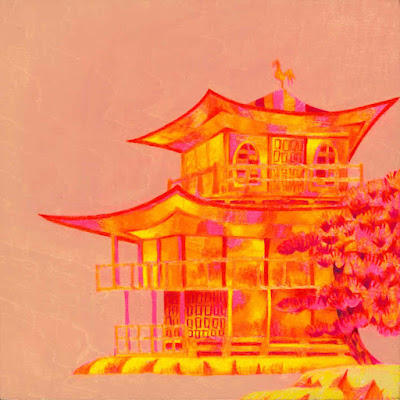*
やるのか、
やらないのか、
どっちなんだい。
どこかで聞いたことの
あるようなフレーズで
始まりました今回。
このご時世、
展覧会の開催自体が不透明で、
今回もまた、
冒頭のような「待機状態」が
あったわけですが。
ありがたいことに、
ぎりぎり2月の末日、
晴れて開催が決定したという
今回の展覧会であります。
さて、
今回の記述。
ただいま開催中の
展覧会のために描いた絵について、
説明代わりにおしゃべりできたらな、
と思ったわけです。
会場でお話できない分、
この場で存分に語らせていただきます。
(・・・て、いつも会場でも、
絵の話なんてしてないけどネ=☆)
*
合板パネルに色鉛筆で描いた、
19センチ角の作品。
1日1枚、
ときには複数枚、
日記のように描いた今回の絵。
1枚1枚の絵について、
短編のようにお伝えできたら
おもしろそうだな、と。
そう思ったからそうします。
今回の『其の1』では、
22作品のうち、
8枚の絵をご紹介いたします。
絵に、言葉など
無用なのではございますが。
描いた者にしかわからぬ
背景やその心情などをお伝えするのも
悪くはなかろうと思います。
全3回でお送りする予定の
シリーズ、其の1。
それではどうぞ、
お好きな感じでお楽しみください。
*
3月3日
#1『お母さんのハンバーグ』
題名そのまま、
おかん(my mother)の作る
ハンバーグの絵。
付け合せにはたいてい、
ポテトサラダorマッシュポテトサラダ、
スパゲッティ(not パスタ)、
さらにフライドポテトが付いていたり、
ときにはバーグに目玉焼きがのっかったり。
副菜に多少の変化はあれど、
ハンバーグ自体に変わりはない。
クローブのよく効いた、
わらじのごときジャンボなサイズの
ハンバーグ。
食べ盛りの中高生じゃ、
ないっちゅ〜の。
な、感じの巨大バーグだ。
あるとき思った。
このハンバーグを、
これまでにいくつ、食べてきたんだろう。
あといくつ、食べることができるんだろう。
人生に行き詰まった、
あるときのこと。
実家にこもって、
身うごきもできなかった。
腹も減らず、
何も食べられない日が何週間か続いた。
毎日、晩ごはんを作っては
置いておいてくれる母。
そのまま食べられずにいると、
机に置かれた「晩ごはん」は、
どこかへ消える。
そしてまた次の日には、
あらたな「晩ごはん」が
机の上に用意されている。
ほんの少し、
手をつけるだけのこともあったし、
まったく箸を取らない日もあった。
そんなことが
繰り返されたある日。
机の上には、
ハンバーグが用意されていた。
横には
見なれた母の達筆の文字で、
短いメモが置かれていた。
「温めて食べてくださいね」
それを見たとき、
涙があふれてきた。
大好きなハンバーグ。
これなら食べるだろうと、
思ったのかもしれない。
これまでに
いくつ食べてきたのかわからない、
おかんのハンバーグ。
このとき初めて、
冷たいハンバーグを食べた。
温めることなく、
そのまま食べた。
本能が戒めを解いたかのように。
気づくと冷たいハンバーグを
ほおばっていた。
まる3日間、
何も食べていなかったせいも
あるだろうけれど。
おいしかった。
冷たいけれど、
めちゃくちゃおいしかった。
冷たいのに、
すごく「あったかかった」。
ハンバーグを食べながら、
涙があふれ出て止まらなかった。
いろいろな感情と同時に、
母への申し訳なさ、ありがたみ、
食べるか食べないのか
わからないのにもかかわらず、
いつまで続くのかわからない状態の中、
今日までごはんを
作り続けてくれたことへの感謝と
申し訳なさがあふれ出た。
ありがとうと、
ごめんねの洪水。
夜中の12時過ぎ、
ひとり泣きながら
ハンバーグを食べた。
食べることは、生きること。
このハンバーグ、
これまでにいくつ、食べてきたんだろう。
あといくつ、食べることができるんだろう。
・・・初っ端から長々と、
湿っぽくて青くさい内容で、
かたじけないでゴメス。
そんなこんなで。
ハンバーグは、
食べるとなくなってしまうので、
絵に描いておこうと思ったわけです。
今回、絵に描いてみて思った。
絵でもこんなに手間がかかるのだから。
本物の「お母さんのハンバーグ」は、
もっと大変だろうな、と。
付け合せのほかに、
サラダとごはん、たまに
ポタージュなんかのスープもつく。
といったわけで。
お母さんありがとう、
と猛烈に思った次第であります。
「お母さんのごはん」を
忘れないように。
テレビの前のちびっこ諸君も、
お母さんに、ありがとう、
ごちそうさまを伝えようね!
ご飯を作ってくれる人は、
みんな「お母さん」です。
*
3月8日
#2『いまはむかし』
「今は昔」
こんな書き出しで始まるのは、
むかしむかしの『竹取物語』。
けれども、この絵は、
かぐや姫とも、昔ばなしとも関係ない。
こんな模様の着物が
あったらいいな。
こんな感じの「浮世絵」が
あったらいいな。
そう思って描いた1枚だ。
そしてこの絵がいつか、
「いまはむかし」になったら
おもしろいな、と。
そう思うのであります。
背景色は、廃盤になった
「ライトグリーン(PC920)」。
自分は主に『カリスマカラー』という名称の、
いかにもカリスマな感じの
米国製の色鉛筆を使っている。
学生のころ、教材で買った『イーグルカラー』。
その商品名が改称されて『プリズマカラー』になり、
現在『カリスマカラー』という呼び名に
落ち着いている。
品番の頭の「PC」は、
プリズマカラー時代の名残りである。
十数年前、
廃盤になったライトグリーン。
その当時、学校で働いていて、
画材屋さんのお姉さんから
廃盤になることをいち早く聞いた。
「なにぃ?! そりゃいかん!」
ということで、
かき集められるだけかき集めてもらって、
何十本か買わせていただいた色。
それがこの「ライトグリーン(PC920)」だ。
画材屋のお姉さん、
どうもありがとう。
ライトグリーン、
まだ何本か、手元にあります。
カリスマカラーは、
色によって若干「におい」がちがう。
ライトグリーン(PC920)は、
塗っていると、
歯磨き粉のような、
少し爽やかなミント調の香りがする。
廃盤色のライトグリーン。
それを背景に使ったこの1枚。
あったものがなくなり、
また新たなものが現れて、
そしてまた消えてゆく。
時間は流れ、動き、
移ろいゆくもの。
ゆるやかでも確実に。
明日が今日に、
今日が昨日に。
すべてが「いまはむかし」
なのでございます。
*
3月9日
#3『西日の金閣』
ご存知かと思われるが、
「金閣寺」という呼び名は本当ではない。
「金閣」というのは建物の呼び名で、
寺そのものの名前ではない。
正確には、
鹿苑寺(ろくおんじ)の「金閣」だ。
ある11月の、
午後4時ごろの風景。
この絵は、
紅葉と夕日に燃える金閣を
思い返しながら描いた1枚だ。
原画では、蛍光色を
ふんだんに使っているので、
この画面上では伝えきれない輝きがある。
この絵も、
「こんな絵があったら飾りたい」
という思いで描いた。
金閣は、
一層(1階)が「寝殿造り」、
二層(2階)が「武家造り」、
三層(3階)が「唐様」と、
時代も様式もばらばらの造りだ。
しかも「全身ゴールド」。
こんないかれた・・・いや、
しゃれた建物が、
たとえ偶然にせよ建立したことに、
拍手喝采、とても長〜い
ブラ棒(ボー)を贈りたい。
三島由紀夫先生の作品、
『金閣寺』に描かれた、燃える金閣。
炎ではなく、
夕日に燃え落ちる金閣も、
大変うつくしい。
*
3月9日
#4『凱旋(がいせん)』
この1枚は、
案内状(DM)のデザインを考えたときに、
頭に浮かんだ絵を描いた。
正方形の、
スカーフのような意匠(いしょう)。
憧れのカレ。
(「彼」ではなく「Carrér」=正方形のこと。念のため)
本当に、スカーフにしたいくらい。
そんなつもりで、描いたつもりの1枚だ。
この絵は「1日1枚」の絵ではなく、
44センチ角の絵。
3月4日から描き始めた。
(冒頭の画像は、制作途中の絵)
描いている途中で、
背景色の色鉛筆「ウルトラマリン(PC902)」が
なくなった。
手持ちの「在庫」を調べてみる。
あるとばかりに思っていた
902のウルトラマリンが、
1本もないことに気づいた。
バイオレット(PC932)や
バイオレットブルー(PC933)、
インペリアルバイオレット(PC1007)は
何本ずつかあったけれど。
ウルトラマリンの予備はなかった。
普段ならすぐさま「世界堂」へ
走るのだが。
このときは買いに出る時間が惜しかった。
なので、ネットで注文した。
ほどなくして、
大阪のほうからやってきた
902番のウルトラマリンは、
やや関西なまりの、
色鉛筆だけにノリのいい
見事なまでのカリスマカラーだった。
ということで、完成した日が
「西日の金閣」の絵と重なっている。
7日、8日を空けて、
この絵は4日間で描いたことになる。
*
3月10日
#5『履きなれたブーツ』
10代終盤、
18歳のときに買った、
黒革の、レッドウイング・
エンジニアブーツ(1993年製:09 /93)。
念願かなって買ったときには、
そのまま履いて寝たいほどうれしかった。
オールソール張り替えで、
新しい靴底(純正)に修繕しつつ。
ぼろぼろではあるけれど、
いまでもずっと履いている。
自分は、
見て描くよりも、
想像で描いたり、
思い出して描くほうが好きだ。
なのでこの絵も、
思い出しながら描いてみた。
色を使った「デッサン」。
そんな気持ちで描いた。
昔、猫を飼っていた。
実家に迷い込んだ白い猫。
名前は「ゴマ」。
頭に胡麻(ごま)をふったような
黒いまだら模様があったので、
そんな名前になった。
お気に入りのブーツ。
ぼくのお気に入りは、
彼(ゴマ)にとってもお気に入りだった。
もちろん履いて出かけるわけではなく、
爪を研ぐための「お気に入り」だ。
目を放すとすぐに抱え込み、
(猫なのに)馬乗りになって爪を研ぐ。
そのたびに「こら」と叱る。
ぼくのお気に入りのブーツは、
いつしかゴマの爪跡で、
穴だらけの傷だらけになってしまった。
当時はその傷がすごく嫌で、
すごくみっともないものに感じた。
歩くたびに気になった。
履いた爪先を見るたび、
もう!と思った。
ゴマがいなくなって。
しばらくすると、
その傷か愛おしく感じられた。
ゴマの残した痕跡、傷跡。
彼はもういない。
けれども彼のしるしがここにある。
ブーツを履いて歩くたび、
ゴマのことを思い出す。
雨の日、雪の日、
アスファルトの上、草の上。
そのほかのことも
たくさん思い出す。
ともに歩んできた、
お気に入りのブーツ。
履き込んで、履きなれた、
お気に入りのブーツ。
・・・ところで。
すり減った靴の「かかと」って、
どこに行くんでしょうね。
世界中に散らばった
かかとたちを集めたら、
ものすごいことになりそうだ。
*
3月13日
#6『マンモス』
マンモス。
毛の長いゾウではなく、
マンモスはマンモス。
マソモスでも
マンモヌでもなく、
マンモス。
愛知万博で、
シベリアの凍土から
掘り出されたという
冷凍マンモスを見た。
それはまるで、
パンダや月の石のような感じで。
行列の末、
なかば夢見心地のような感じで見た、
不思議な「物体」だった。
何かの技術が発達して、
生きた、動くマンモスが見てみたい。
かつて東ハトのお菓子で、
『マンモスの肉』というスナックがあった。
初回の登場時より、
二度目の「再来」時のほうが、
形も食感もおもしろく、
味もおいしかった。
マンモスにも会いたいけど、
『マンモスの肉』にも、
また会いたい。
*
3月14日
#7『あげる』
道ばたに生えている、
きれいな花。
それを摘んで、
誰かにあげる。
あげたい、と
思うその気持ち。
ただ「あげたい」と思う、
純粋なその気持ち。
その気持ちは、
花のようにうつくしい。
道ばたの、
名もなき花を贈られて。
よろこぶ人の心もまた、
うつくしい。
絵の中の女の子は、
スカートに咲いた花をひとつ、
差し出すのでした。
*
3月15日
#8『虹色マンモス』
化石や骨格が見つかり、
かつて生存していた姿を
再現された恐竜たち。
どれだけの検証を重ねても、
生きていた当時の姿は、
想像の範囲を超えないという。
特に体表の色は、
何の根拠も手がかりも残っていない。
体毛の有無もそう。
そう考えると、
マンモスの毛が何色かどうかとか、
どんな毛の長さだったのかも
決め手がないかもしれない。
凍土などから見つかった
マンモスの毛。
茶色く見えるその毛も、
実は、植物などが枯れるように、
朽ちて退色しただけだとしたら。
赤とか青とか金色とか。
虹色のマンモスがいたって
わるくない。
茶色いマンモスの絵を描いたあと、
見てみたいなと思って、
描いた1枚。
マンモスの絵は、
大きなパネルでも
また描きたいと思った。
*
いかがでしたでしょうか、
おしゃべり絵画鑑賞会。
お気に召された方は、
引きつづき次回もお楽しみください。
それではまた、
『其の2』でお会いしましょう。
< 今日の言葉 >
Sorry. "ambassador",
I mistakenly heard that it was a delicious carbonated drink.
Excuse me, can you talk to me again from the beginning?
ごめんなさい。『アンバサダー』のこと、
ずっと美味しそうな炭酸飲料だと思って聞いていました。
すみませんが、もう一度最初から話してもらってもいいですか?
(『英会話:こんなときあんなとき、とっさのひと言』/イエハラ・ノーツ2022より)