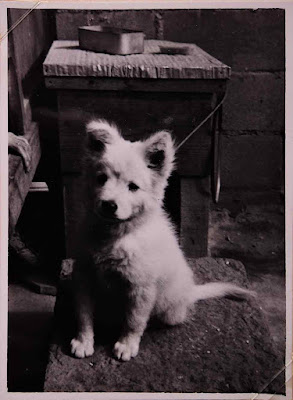*
昔の人は、トイレのあと、
わらでお尻を拭いていた。
砂でこすって、
その手を水で洗ったり。
葉っぱや新聞紙できれいにしたり。
トイレの横にわら縄が、
綱渡りのように張ってあり、
そこにまたがってお尻を拭いた、
という話を、昔、本で読んだ。
わかるかな、と思いつつ、
それを相手に話してみた。
話し相手というのは、母のことである。
「知っとるよ、それ」
「え、知ってるんだ」
「見たことはないけど、
聞いたことはある」
言ってみるものだ。
そこで、トイレ談義に花が咲いた。
韓国の旅館(リョグァン)のトイレは、
和式だったけど、
お尻側が扉に向いているのではなく、
顔側がこちら(扉側)に向いていた。
つまり、うっかり開けたら、
お尻ではなく、
顔と顔とが鉢合わせになるのだ。
「なんでだろうね」
母が、首をかしげる。
文化のちがい。
それで思い出したのが、
たしかフランスだったか、
知らない人に裸を見られたとき、
胸などではなく、
顔を両手で隠すのだと。
「顔を隠して、
自分が誰だかわからなかったら、
裸を見られても
恥ずかしくないんだって」
顔を隠す文化と、裸体を隠す文化。
もっと言えば。
紙でお尻を拭く人と、
水流でお尻を洗って育った人とでは、
価値観や感覚にちがいが出てくるはずだ。
「昔の人は、立ってしとったもんね。
男も女も、立ったままで」
そんな光景を見たことがあると、
母が言った。
現代では逆に、
男性でも座って用をたす人が
増えている。
『言葉が思考をつくり、
思考が行動をつくり、
行動が習慣をつくり・・・』
ではないが。
行動がちがえば、思考もちがい、
使う語彙(ボキャブラリー)も、
伝わる言葉もちがう。
言葉、思考、行動、習慣。
その循環(ループ)がまた、
その人の価値観を育み、
踏み固めていく。
母とぼく。
ぼくと母。
家族だけど、やっぱり違う。
遺伝子、環境、家庭、家族。
同じだった家を巣立ち、
ちがう「釜の飯」を食べ、
まったくちがう環境で、
まるでちがうものを見てきた。
好みや志向、習慣も変わり、
価値観も変わった。
世代、年代、性別、志向。
もともとちがった部分もある。
それでも、母と話すうち、
母も「おなじ人間」で、
年はとっても、
共感できる部分や発見が
たくさんあって、
おもしろいと思った。
母に、
タイで体験(洒落じゃなく)した
トイレの話を伝えた。
タイのトイレには、
日本のコンビニなどで見かける
清掃用のホースのような、
ノズル付きの洗浄器具が、
便器のかたわらに設置してある。
そのホースでお尻を洗浄し、
備えつけの紙(ロールペーパー)は、
あくまで水気を吹き取るもので、
汚れたお尻を拭くものではない。
使用した紙は、
便器に流すのではなく、
個室内のすみに置かれた
くすかごに捨てる。
なので、まちがっても
いきなりお尻を拭いた紙を
捨ててはいけないし、
便器に紙を流してもいけない。
スーパーマーケットのトイレでは、
英語の注意書が貼られていたが。
おそらくタイでは「常識」のはずだ。
食事をする机の上には、
日本でよく目にするような形状の、
ロールペーパーが置かれていた。
通常「トイレットペーパー」と
呼ばれるそれが、
食卓に置かれているのだ。
タイの人に聞いたわけではないが。
タイ映画などを見ていて、
代用ではなく、それがタイの
「ティッシュペーパー」なのだと知った。
(ちなみに「芯」は付いておらず、
「外周」からではなく、
「内側」から紙を引き出して使う)
そう。
価値観というものは、
こんなものだ。
誤解した見解。
文化のちがい。
考え方の相違。
紙か水か。顔か裸体か。
こんなことでむきになって、
争うことこそ、価値がない。
上記のタイ体験(洒落ではなくて)を
母に伝えるのに、
回り道をしたり、たとえ話をしたり、
語彙を嚙みくだいたりして、
ずいぶん手間がかかった。
そう。
これも価値観のちがい。
価値観や文化がちがえば、
理解するのに時間がかかったり、
間違って理解してしまったり、
まったく理解できなかったりもする。
知識や情報として頭で理解できても、
感覚的に、体感としては
理解できないこともある。
酒に酔ったことがない人に、
酩酊感を伝えるのは難しい。
煙草を吸ったことのない人に、
喫煙の意味を伝えることは
かなり難題だ。
体験、体感、経験。
実体験での「見識」は、
机上の知識の物差しでは
とうてい測りきれない。
そこで必要になるもの。
それが、想像力。
読んで字のごとく、
想像をする力のことだが。
これが貧しいと、
自分以外の世界が、
理解できない。
想像力。
ファンタジーや空想ばかりが
想像ではない。
人を思いやる気持ち。
想像力は、
思いやりの源泉である。
母と話す日々の中、
今までには考えなかったようなことを
考えるようになった。
友人などに話すのとは当然ちがい、
子供に話すのともまたちがう。
年寄りだから、ということでもない。
「母」と話すには、
「母」に伝え、伝わることが必要なのだ。
「母」とは、誰かの母ではなく、
目の前にいる、自分の母親。
一般名詞てはなく、固有名詞。
ほかの誰でもなく、
愛称「エミリィ」である、
わが「お母さん」に伝わる
言葉、温度で話す必要がある、
ということだ。
この発見は、
まるで稲妻のように全身を貫き、
せまく曇っていた視界を
洗い流すほどの勢いがあった。
洗い流されて初めて、
自分の視野がせまく
曇っていたことに気づいたほどだ。
目が開いた、というか。
おかげで日々、新鮮な驚きがある。
母と向き合う時間の中で、
これまで感じたことがないほど、
学びと収穫、衝撃的な発見が
連日、怒涛のように、
あるいは川のせせらぎのように、
尽きることなく続いている。
これは、
ぼくだけの個人的な体験なのか。
ほかの人たちも、
もし同じような状況で
誰かと向き合ったら、
ぼくが感じるような驚きと発見を
感じるのか。
母という、家族であるはずの人を、
気づけば他人のように、
いやむしろ、家族だからこその、
「家族的な距離感」で接してきた結果
できあがった微妙な関係性。
今ぼくは、
母を「一人の人間」として見ている。
一人の歴史ある人間として、
接している。
家族であっても。
親ではあっても。
「別の個性」である。
これまで、
家族だからこその甘え」があった。
家族だから許される、
わかってもらえている、
というおごりがあった。
ぼくはこれまで、
母から「もらってばかり」だった。
してもらう、買ってもらう、
作ってもらう、ゆずってもらう。
わかってもらって、どいてもらって、
聞いてもらってきた。
母はどうだ?
父がおらず、みなが出て行き、
一人ぼっちだった母は、
誰に「もらって」きたのか。
母の日や誕生日、
その他いろいろな節目に、
母にはいつも「あげて」きた。
けれども。
それは、
明らかに物質的で、
刹那的で一方的で、
そこに「想像」の力は
働いていなかった。
料理好きな母は、
誰かに手料理を
食べてもらうことを喜んだ。
母の手料理を食べることを
ひとつの「親孝行」だと思い、
数年前から続けてきた。
点ではなく、面で接すること。
面で接してみて、わかったこと。
想像すること。
想像していた以上に、
自分の想像力が足りていなかったこと。
先回の記述の
続きのようになってしまったが。
元気になった母は、
生き生きと今日のことを語り、
昔話を語り、
何度も同じ話をしたり、
まったく新しい話を聞かせてくれたり、
何より毎日、笑顔でいっぱいだ。
「母さんが子供のとき、
好きな科目って何だった?」
「お母さんはねぇ、
数学とか、英語が好きだった」
「それって、その科目の先生が
好きだったからでしょ?」
これまでの話からの推測だったが。
事実、そのようだった。
「じゃあ、アルファベット、
全部言える?」
「言えるに決まっとるでしょ。
A、B、C、D、E、F、G、
H、I、J、K、L、M、N。
O、P、Q、R、S、T、U、
V、W、シックス・・・あれ、
ちょっと待ってよ。
A、B、C、D、E、F、G、でしょ。
H、I、J、K、L、M、N。.
O、P、Q、R、S、T、U、
V、W、シックス、エイト・・・あれ、
ちょっと待ってよ、
A、B、C、D、E、F、G・・・・」
ぼくは、腹を抱えて笑っていた。
* *
価値観のちがう母に、
自分の思っている、
または感じている観念を伝えるのは、
なかなか根気が必要な場面がある。
「来年は、へび年だね」
「そうだね」
「へびは、長寿とか、命の象徴で、
縁起のいいものだって
言われてきたらしいね」
「なんでそんなこと言うのかねぇ」
「脱皮するでしょ、へびって。
脱皮ってわかる?」
「わかる。
財布に入れたりするやつでしょ」
「そう、それ。
それを見た昔の人は、
へびが死なずに
生まれ変わってるって
思ったらしいよ」
「猿も、縁起がいい動物だよね」
「猿が桃を持ってる置き物とか、
あるもんね」
「桃もいいの、縁起?
お尻みたいな形しとるけど」
「なんか、昔の古墳の中から、
桃の種がいっぱい
出てきたらしいよ。
種だけを集めて、
偉い人のお墓に埋めたんだって。
生命の源とかで、桃の種が、
崇められてたみたい。
母さん、古墳ってわかるよね?」
「わかる、こういうのでしょ」
母が、手を動かし、謎の動作をする。
よく見ると、空に「古墳」を
描いているようだ。
「そうそう、そういうの」
・・・なんていう、
他愛のない会話が、
年齢も文化もちがう価値観を
突きくずし、
均(なら)していってくれる。
旅行好きな、
母の友人の話になって。
「ほら、なんていうの、
なんやらっていう、あれ」
「ボーイスカウト?」
「そうそう。
で、ああいうとこに泊まるの、
ほら、なんやらっていう」
「民宿?」
「そうそう」
われながら、
正解率が高い時には、
小おどりしてしまう。
「ほら、なんだっけ。
なんとかっていう、あれ。
ほら、あるでしょ、あの、
あそこにあるやつ」
わかっていても、
ときどき母の回答に任せてみたり。
野宿の話になって、
母が言った。
「クマとか出てきたら、怖いがね」
「クマも、本当は怖いんだよ」
「そんでも、
クマに襲われた話とか、
よく聞くがね」
「出会っちゃったから、襲うんだよ。
本当は怖くて、
出会いたくないんだよ、人間と。
クマよけの鈴ってあるでしょ。
あれで『ここにいるよ!』って
知らせて、
クマのほうに逃げてもらうんだよ」
「たしかにクマって、
ぬいぐるみにもなっとるくらいだし。
犬みたいでかわいいもんね。
ぬいぐるみのほとんどが、
クマじゃない?」
母の、少々めちゃくちゃな見解も、
素朴だからこそ斬新で、
なるほど、と思わされたり。
「たしかに、
クマのキャラクターって、多いね」
とか言いつつも。
あらためて文字にして読み直すと。
『ぬいぐるみのほとんどが、
クマじゃない?』
やっぱりむちゃくちゃで、
じわじわと笑いがこみ上げる。
* * *
言っても母は「昔の人」だ。
価値観も「最新」ではなく、
現代の文化や情報、
外国の風習や文化に
明るいわけではない。
そういう自分も、
決して「最新」ではないが。
いわゆる「偏見」に対する考え方は、
母より開けている部分も多少ある。
一般的な、ひと昔前の、
ごく平凡な「価値観」。
そのほとんどが、
教育と情報が下敷きで、
実体験や経験に基づいたものではない。
偏見。
ステレオタイプ。
それはほとんど、
「大衆文化」に等しい。
「あっちの人は、みんな裸で、
服とか着てないんでしょ?」
「いやいや、そんなことはなくて。
もちろん、そういう種族もいるけれど。
そういう人は、多分だけど、
観光客の前に
出てきたりはしないと思う。
そういうのは、たいてい、バイトだよ。
腕時計もしてて、携帯も持ってて、
終わったら車乗って帰るよ」
「車! そうなの?」
「映画村の
お侍さんみたいなもんじゃない?
ちょんまげの人なんていないでしょ」
「そうだねぇ。そういうことか」
まるで、
いい加減な「大人」が、
大きな「子供」と
話しているようで。
話せば話すほと、勉強になる。
話すたびに、
凝り固まった価値観が、
ぽろぽろと突き崩されるのがわかる。
母が買い物へ行ったとき。
たい焼きの焼ける甘い香りに誘われて、
ついカートから離れてしまった。
たい焼きを買って、ふと気かつくと、
買ったばかりの買い物袋がない。
カートをどこに置いたのか。
まったく記憶がない。
「警備の人に聞いたりして、
30分くらい、くりくりくりくり
探し回っとったもんで。
帰りが遅なってまったかね」
「けど、見つかってよかったね」
「ほんと。もういっぺん
買い直さないかんかと思ったけど。
よかたぁって思った」
「財布とか入れてなくてよかったね」
「そうなんだわ。
とぉろいねえ、母さん。
自分でも嫌になっちゃうわ」
「何にせよ、無事でよかったね」
「本当、よかったわぁ。
うろうろ探し回って、疲れちゃった。
お母さん、方向音痴だでいかんわ。
駐車場でも、
自分の車をどこに車停めたか
わからんようになるもんで。
たいてい2、30分くらいは、
ぐりぐり探し回って、
係の人に聞くんだわ。
ほんとばかだねぇ。ばか、ばか。
今度から気ぃつけないかん」
「って言って、またやりそうだね」
「そうかもしれん」
二人で声を上げて笑った。
先日、歯医者の待合室で、
名前を呼ばれたおじいさんが、
ソファから立ち上がろうとして、
なかなか腰が持ち上がらず、
立ち上がりかけてまた座る光景を見た。
立ち上りかけて座った母が、
「いかんわぁ。
ずっと座っとったせいで
立てんかった。もう年だわ」
と言うのを聞いて、
歯医者での光景を思い出した。
母に話すと、声を上げて笑った。
「笑っちゃいかんのだけど。
笑っちゃうね、そんなの見たら」
たしかに。
笑っちゃいかんのだけど、
そんなのを見たら、笑っちゃう。
ゆっくりと立ち上がるおじいさんに、
歯医者の人は、
笑いながら近づいて、
手を差し伸べた。
「ごめんね、
長い時間待たせちゃって。
体が固まっちゃったね」
それを聞いた母が、
「気の利いたこと言うねぇ」
と、感心した。
価値観。
同じ風景、同じ場面でも、
人によって、感じ方はちがう。
現場にいても、いなくても。
想像すること。
笑っていいこともあるし、
笑っちゃいけないこともある。
けれどもなるべく「笑って」いたい。
普遍なもの。不易なもの。
母から教わる、平和的な心。
人を疑わない母の、のんきな視線。
年長者から学ぶことは多い。
今日、母が何かをやらかして、
二人ですごく笑った。
それが何だったか、
少しも思い出せないけれど。
すごく笑ったことだけは、
しっかり覚えているし、
その風景はくっきり焼きついている。
母の笑顔。
エプロンを着た母が、
フライパン片手に笑っている。
自分では見えていないけれど。
笑う母の顔と、
そっくり鏡写しのぼくが
いたはずだ。
想像すること。
ずっと一人だった、母の心。
想像して、気づけてよかった。
法則でもメソッドでも模範回答でもなく。
これは、ぼくの導き出した「こたえ」だ。
正解ではない。
ぼくだけの「こたえ」。
同じばかでも、ぼくは、
不幸の種をばら撒くばかにはならない。
価値観と想像力。
知識や情報が、時にそれを阻害する。
万能薬は、どこにもない。
目の前の景色をじっくり見て、
じっと観察すること。
こたえに向かって歩く過程。
こたえは心の中にある。
全部、そこにそろっている。
使い方を知らないだけ。
使わずにしまい込んでいるだけ。
気づかないうちに、
忘れてしまっただけ。
使い方を、
どこにしまい込んだかを、
忘れているだけ。
おしゃれなのが、センスではない。
センスとは、
いちばんいいものを選ぶ力。
センス。感性。感覚。
忘れてませんか、使い方を。
眠らせてませんか、
本当の自分の感性を。
「あんたはあんたのままでいい」
母がよく、言ってくれた言葉。
忘れかけていたことを、
母が思い出させてくれた。
忘れていた感覚を、
母がゆさぶり起こしてくれた。
想像とは、ゆるすこと。
「いいよ」という、肯定的な感覚。
理解しようという気持ちが、
価値観の垣根を越えて、
おたがいの感性を新たにしてくれる。
ぼくが欲しかったもの。
想像力。
想像する力。
まだ手に入れたわけじゃなくて、
ようやくそれがわかっただけ。
わかる人には、わかる話。
わからない人には、わからない話。
価値観、感性、想像すること。
目の前に、
こんなうつくしい景色が
広がっているのに。
それに気づけないのは、
さみしいことだから。
ぼくは、目を開けて、
うつくしい景色を見ようと思う。
朝起きて、
全粒粉のパンがなくなっていた。
どうやら母が食べたらしい。
「あんたが買ったやつだった?
ごぉめん、まちがえて食べちゃった」
「おいしかった?」
「おいしかったぁ。
あんなの、初めて食べた」
母が、おいしかったのなら、
それでいい。
怒っても、笑っても。
地球は丸くて、
今日もまわりつづける。
だったらぼくは、
笑っていたい。
父なら怒るだろう場面でも、
ぼくは、笑うほうを選ぶ。
『人はパンのみに
生くるにあらず』
『パンがなければ、
お菓子を食べればいい』
昔の人は、いいことを言いますね。
朝からスナック菓子を
食べてもいいじゃないか。
お菓子を食べても、
スナックみたいにカリカリと、
かたいことは、言いっこなしです。
< 今日の言葉 >
『かかしは、自分の頭の中に
すばらしい考えがわいてくると、
仲間たちにいいました。
けれども、自分だけにしか
わかりようがないので、
すばらしい考えが何なのか、
ひとことも説明しませんでした』
(『オズの魔法使い』L・F・バウム作 より)